税理士のみなさん、最新記事「Who are AI browsers for?」は読みましたか?
OpenAIが新しいAIブラウザ「ChatGPT Atlas」をリリースしたことが話題になっています。
ただし、テッククランチの記者たちが実際に試してみた結果は「期待ほどではない」というのが正直なところ。AI技術とビジネスの現実のギャップが、ここにも現れています。
元記事を5つのポイントで要約
- OpenAIがChatGPT Atlasという新しいAIブラウザを発表、自動でネット検索やタスク処理をするAIエージェント機能を売りに
- 実際に試した記者の評価は「効率化は微々たるもの。ほとんどの場合、AIが画面をクリックしまくるのを眺めるだけ」
- 普通のユーザーが本当に欲しい機能なのか、需要と供給のギャップが大きい
- 過去のブラウザ競争でも、既存のSafari・Chrome・Firefoxに勝つのは不可能だと証明されている
- OpenAIが強いのは、莫大な資金力で「お金にならなくても継続できる」という点だけ
税理士がAIブラウザから学ぶべき現実
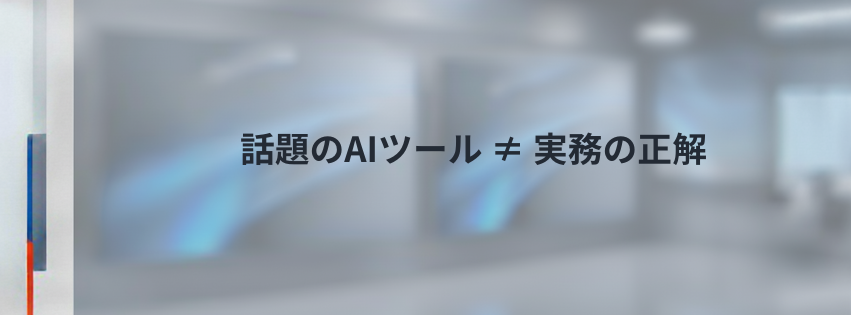
華々しいAI技術も、実務では役に立つとは限らない
AI技術と実際の業務改善には大きな距離があります。
ChatGPT Atlasの話も全く同じです。
テックメディアは「AIエージェントが自動でネット検索してタスクを実行!」と派手に報じます。
でも、実際に使ってみると「レシピを検索してInstacartに食材を追加する」なんて誰もやっていない。AIが画面をクリックしまくるのを眺めるのに、何の楽しみがあるのか。この正直な指摘が、今のAI業界の本質を突いています。
税理士業界でも、同じような「夢」と「現実」のズレが生まれています。
「AIが決算書を自動で作成できる」「税務調査対策を完全自動化」。こんなうたい文句で新しいツールがリリースされますが、実際に導入してみると「結局、最後は手作業が必要」「ツール自体が複雑で使えない」という現実に直面します。
流行っているからと飛びつくのは危険
ChatGPT Atlasのような新しいツールがリリースされると、すぐに「試してみたい」と思う人もいます。
テックに強い記者たちですら「実用性には疑問」と評価しているのに、一般的な業界人が使いこなせるはずがありません。
税理士も同じ。
新しいクラウド会計ソフトやAI給与計算ツール、経営分析AIが出てくるたびに「これはいいらしい」と契約してしまう。でも、実際には既存システムで十分だったり、導入コストに見合う成果が出なかったりします。
新しいツールを試す前に、「本当に必要か?」「現在の業務で実際に活かせるか?」「スタッフが使いこなせるか?」この3つを問い直す癖をつけましょう。
ブラウザ市場の歴史が教えるもの
大手に勝つのは「資金力」だけ。技術力ではない
記事で興味深い指摘があります。
「過去、何度もSafari・Chrome・Firefoxに対抗するブラウザが現れたが、全て失敗している。ブラウザだけでは商売にならないから」。
つまり、技術力の高さや革新的な機能では勝てず、結局は「どれだけ長くお金を燃やし続けられるか」という資金力の勝負になるのです。
OpenAIが強いのも、高度なAI技術があるからではなく、莫大な投資ラウンドで数年は赤字でも続けられるという点だけ。
税理士業界に置き換えると、大手会計ソフト企業(freee、マネーフォワード、弥生など)が圧倒的な地位を保つのも、技術が最高だからではなく、マーケティング力と資金力を使って市場を支配しているからです。
中小企業や個人開発者がいくら優れたツールを作っても、資金力と営業力がなければ日の目を見ることはありません。
パイオニアが常に勝つとは限らない
一方で、パイオニア企業が必ず成功するわけではありません。
記事でも「既存のブラウザが十分に使える状況で、わざわざ乗り換える理由がない」という指摘があります。
税理士が新しいツールを導入する際も、同じ心理が働きます。
freeeやマネーフォワードで十分に記帳できるなら、新しいAIツールに乗り換える動機は弱いのです。「もっと便利になる」という期待だけでは、変更のコストに見合いません。
セキュリティリスクという忘れられた課題
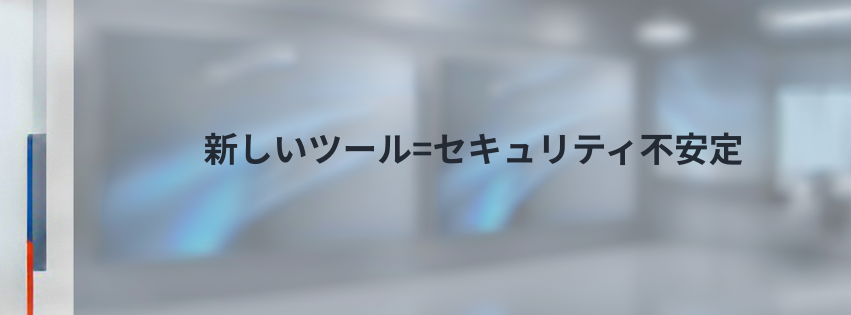
AI機能には「重大なセキュリティリスク」がある
記事で触れられているのに、ほとんど議論されていないのが「セキュリティリスク」です。
AIエージェントがネット上をクリックしまくるという機能は、裏を返せば「第三者のサーバーを通じて、あなたの情報を送受信しまくっている」ことを意味します。
税理士にとって、これは死活問題です。
顧問先の個人情報や財務情報を扱う税理士が、セキュリティが不確実なAIツールを使うわけにはいきません。
- AIエージェントが自動で複数のウェブサイトにアクセス→情報漏洩の可能性
- ツール経由で送信されたデータが、どこに保存されるか不明確→コンプライアンス問題
- 新しいツールほどセキュリティ監査が不十分→サイバー攻撃の標的になる可能性
- 顧問先からの「このツール使ってるの?」という質問に答えられない→信頼喪失
新しいAIツールを試す前に「このツールのセキュリティ体制は大丈夫か?」「個人情報をどう扱っているか?」を確認することが重須です。
古いツールが「安全」とは限らない
逆に、古いツールが安全とは限りません。
重要なのは「定期的なセキュリティアップデート」「外部の監査」「情報公開」です。
大手会計ソフトベンダーは、これらを明記しています。
freeeなら「ISO 27001認証」「定期的なセキュリティテスト」といった情報がオープンになっており、大事な情報を預けるに値します。
新しいAIツールを選ぶ際は「機能の便利さ」ではなく「セキュリティ情報の透明性」を重視しましょう。
結局、ツール選びで失敗しない法則

話題のツールより、今の課題解決を優先
ChatGPT Atlasの例を見ても、テック業界の「最新=最高」という固定観念は危険です。
税理士業界も同じです。
新しいツールを試す前に、現在の事務所の「本当の課題」が何かを明確にすべきです。
| よくある失敗 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 「最新のAIツールが出た」→すぐに契約 | 「月次処理に3日かかる」→それを解決するツールを選ぶ |
| 「業界みんな使ってる」→うちも導入 | 「うちの業務フローに本当に合うか」を検証 |
| 「できるだけ高機能」を優先 | 「使いこなせる機能」を優先 |
| セキュリティは二の次 | 顧問先の信頼と情報保護が最優先 |
実務レベルで「本当に役に立つか」を試す
新しいツールを導入する際は、必ず「トライアル期間」を使いましょう。
ChatGPT Atlasの記者も「実際に使ってみたら、想像と違った」と指摘しています。
税理士なら、新しい会計ソフトを導入する前に「うちの顧問先のデータで試してみる」「スタッフに実際に使わせてみる」「1ヶ月運用してみる」という段階を踏むべきです。
最初から本運用に移すのではなく、小さく試して「本当に効率化できるか」を確認する。その結果が良ければ導入、ダメなら他を探す。この慎重さが、無駄な投資を防ぎます。
税理士が2025年に忘れてはいけないこと
AIツール選びは「流行」ではなく「実務」で判断すべき
テック業界の華々しい報道に惑わされず、自分たちの業務に何が必要か。これを冷徹に判断する力が、今ほど大切な時代はありません。
ChatGPT Atlasのような「未来のツール」は、確かに魅力的です。
でも、現在の税理士の課題は「スタッフの作業時間削減」「顧問先満足度向上」「セキュリティ確保」といった地道な改善です。派手なAIより、地味で確実なツール選びが、事務所の競争力を高めるのです。
過去のブラウザ戦争から学べることは「資金力と営業力がある企業の新ツールは、必ずしも業界標準になるとは限らない」という現実。
税理士業界でも、大手がリリースする新機能が「本当に必要か」を自分たちで判断する勇気が必要です。
新しさよりも、実用性。
流行より、実績。
この判断軸を持つ税理士事務所が、これからも顧問先からの信頼を勝ち取り、スタッフからも選ばれ続けるのではないでしょうか。
よくある質問と回答
Answer 現時点では必須ではありません。ChatGPT Atlasのような最新AIブラウザは「実験段階」であり、実務で使える段階には至っていません。税理士業務では、むしろ既存のブラウザ(Chrome、Safari、Edge)と専門的な会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計)の組み合わせで十分です。新しいツールに飛びつくより、今使っているツールを使いこなすことが先決でしょう。
Answer AIエージェントは自動で複数のウェブサイトにアクセスし、情報を送受信します。この過程で、顧問先の財務データや個人情報が意図せず外部サーバーに送信される可能性があります。また、新しいツールほどセキュリティ監査が不十分なケースが多く、データ保存場所や暗号化方式が不明確な場合も。税理士は守秘義務があるため、セキュリティ認証(ISO 27001など)を取得していないツールの使用は避けるべきです。
Answer 大手だからといって盲目的に導入する必要はありません。OpenAIのような資金力のある企業は、収益化できなくても数年は運営を続けられますが、それは「優れた機能がある」という証明にはなりません。記事でも指摘されているように、実際の使用感は「微々たる効率化」にとどまることが多いのです。まずは無料トライアルで実際に試し、自分の事務所の業務フローに合うかを確認してから判断しましょう。
Answer テック業界には「新しい技術を売り込むことで投資を集める」というビジネスモデルが存在します。実際のユーザーニーズよりも、投資家へのアピールや話題性を優先している場合も少なくありません。税理士にとって重要なのは「流行っているか」ではなく「実務で本当に役立つか」です。既存ツールで業務が回っているなら、無理に新しいツールに移行する必要はありません。
Answer 3つの基準で判断してください。第一に「現在の課題を解決できるか」。月次処理に時間がかかるなら自動仕訳機能、顧問先対応が多いならレポート自動生成など、具体的な課題に対応したものを選びます。第二に「スタッフが使いこなせるか」。高機能でも複雑すぎては意味がありません。第三に「セキュリティ体制が明確か」。ISO認証や定期的な監査があるかを確認しましょう。この3つをクリアしたツールだけを導入候補にすることで、失敗を防げます。

