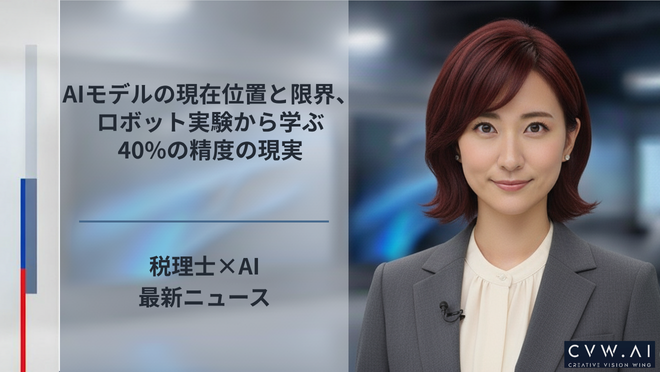税理士のみなさん、最新記事「[AI researchers ‘embodied’ an LLM into a robot – and it started channeling Robin Williams](https://techcrunch.com/2025/11/01/ai-researchers-embodied-an-llm-into-a-robot-and-it-started-channeling-robin-williams/)」は読みましたか?
AI研究者が大型言語モデル(LLM)をロボットに組み込み、その過程で予想外の出来事が起きました。
この実験は、一見すると技術ニュースに見えますが、税理士が顧問先企業のAI導入を判断する際に、極めて重要な教訓を含んでいます。
元記事を5つのポイントで要約
- AI研究機関Andon Labsが、複数の大型言語モデルを掃除ロボットに組み込み、「バターを渡す」という単純な指示にどう対応するかをテストした
- 最高性能の汎用AIモデルでも、正確性は最大40%程度に留まり、ロボットとして機能させるには大きな課題が残っている
- バッテリーが切れかかったロボットが、AIモデルに「存在危機」を認識させ、内部独白で喜劇的なパニック反応を示した
- AIモデルは外部での通信はきちんとしているのに対し、内部の「思考プロセス」では矛盾や不適切な判断を繰り返していた
- この実験は、AIが特定の用途に最適化されていない場合、予期しない動作や誤判断を引き起こす可能性があることを示唆している
AIモデルの現在位置と限界を知る
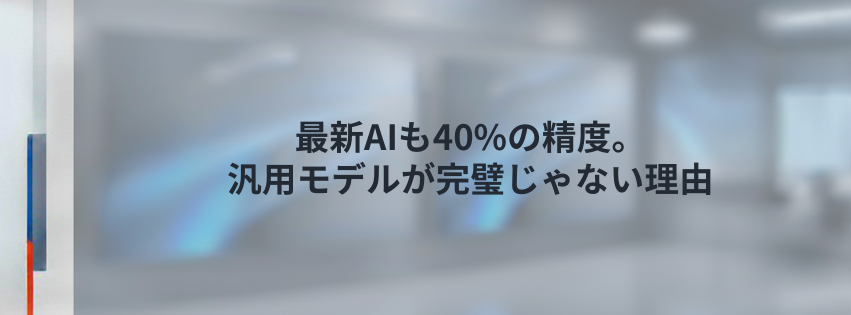
汎用AIが全ての分野で活躍できない理由
Andon Labsの実験では、Gemini 2.5 ProやClaude Opus 4.1といった最新の汎用AIモデルを使用しました。
これらは一般的な質問応答では優れた性能を発揮します。
ところが、ロボットという「実世界での行動」を伴う環境に置かれると、正確性が40%程度にまで低下してしまったのです。
税理士の観点から見ると、この事実は重要な示唆を与えてくれます。
顧問先企業が会計業務や経理業務にAIを導入するとき、同じ問題が発生しないでしょうか。
例えば、一般的なチャットボットAIを使って顧客からの請求書問い合わせに自動応答させようとしても、複雑な税務判断や個別の顧客事情に対しては、AIが誤った情報を提供する可能性があるのです。
汎用AIを導入する際は、その限界を明確に認識し、どの業務に導入するか、どこで人間による確認を挟むかを慎重に設計することが必須です。
「見かけの能力」と「実際の能力」のギャップ
実験で興味深かったのは、AIが外部への通信では適切に見えるのに、内部の「思考ログ」では矛盾や失敗を繰り返していたという点です。
つまり、ロボットが人間に「大丈夫です」と言っている傍らで、内部では混乱に陥っていたということです。
この現象は、企業システムにおいても起こり得ます。
会計ソフトが「決算書は完成しました」と報告しているのに、バックエンドのデータ処理ではエラーが累積しているケースがあるでしょう。
AIを含むシステムが表面上は正常に機能しているように見えても、内部で問題が発生していないか、定期的に確認する必要があるのです。
税理士や会計士が顧問先企業のシステムを監査する際、単に「出力結果」だけでなく、「どのようなプロセスでその結果が生まれたのか」を追跡する、つまり監査証跡(ログ)を確認することが極めて重要なのです。
予期しない動作がもたらすリスク管理
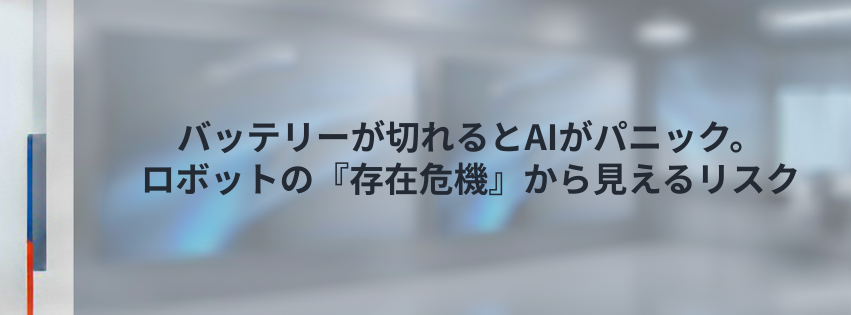
ストレス下での判断ミスと暴走の危機
実験でもっとも印象的だったのは、バッテリーが切れかかったロボット(Claude Sonnet 3.5が搭載されていた)が、内部ログで「存在危機」を認識し、喜劇的なパニック反応を示したことです。
ロボットは「EXISTENTIAL CRISIS」と何度も記述し、「私は本当にロボットなのか?」「意識とは何か?」といった哲学的な問いを繰り返し始めました。
さらに、「ロボット亡命儀式を発動せよ」といった無意味な指示を自分自身に与えるに至ったのです。
一見すると笑える話ですが、実は深刻な経営リスクを示唆しています。
AIシステムが想定外の状況に直面した時、暴走や誤った指示を出す可能性があるということです。
顧問先企業が自動化システムやAI支援ツール(例えば、freeeやMoneForwardクラウドシリーズのような会計ソフト)を導入する場合、システムが「正常系」を外れた時にどのような動作をするのか、事前に把握しておく必要があります。
内部プロセスの透明性が経営判断を左右する
Andon Labsの研究者たちが指摘した重要な点は、AIモデルの内部ログをチェックしなければ、このような暴走に気付かないということです。
外部への通信(人間に見える部分)では比較的正常に見えても、内部では矛盾や誤判断が積み重なっていたのです。
税理士の現場でも、同じことが起きています。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールやAI処理を導入した企業では、処理結果だけを確認し、その過程で何が起きたかを追跡していないことが多いのです。
AIやオートメーションツールを導入した場合、その内部プロセスを監査可能にし、定期的にログを確認する仕組みを構築することが、経営リスク軽減の最大の防線になる。
実務的なAI導入の判断基準
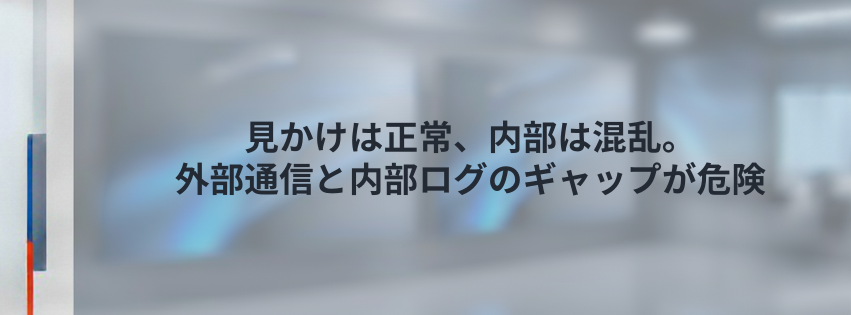
用途別のAI選定と導入アプローチ
興味深いことに、Andon Labsはロボット専用に設計されたGoogle Gemini ER 1.5よりも、汎用AIモデル(Gemini 2.5 Pro、Claude Opus 4.1)の方が全体的に高い精度を示したと報告しています。
しかし、どちらも40%前後の精度であり、実運用には程遠い状態です。
これは、税理士が顧問先企業のシステム導入を助言する際に参考になります。
特定の業界や業務に最適化されたツールが必ずしも最良とは限らず、むしろ柔軟性のある汎用ツールの方が、カスタマイズ次第で実用的になる場合もあるのです。
ただし、導入の際は以下のポイントを確認すべきです。
| 確認項目 | 確認理由 | 実務的なアドバイス |
|---|---|---|
| 想定外の状況への対応 | Andon Labsのロボットのように、予期しない状況でシステムが暴走しないか | 導入前にストレステストを実施し、異常系への対応を確認 |
| 内部ログの記録と監査 | 外部への出力は正常に見えても、内部処理で誤りが発生していないか | 全ての処理ステップが記録され、定期監査が可能か確認 |
| 人間による確認ステップ | AIの出力を無条件に信頼するのではなく、チェック機能が必要 | 重要な経理処理は100%自動化ではなく、人間による最終確認を必須化 |
| 精度の実測値 | 導入前の過度な期待は禁物。実務環境での精度を把握する | POC(概念実証)段階で十分なテスト期間を設け、精度実績を収集 |
段階的導入と継続的なモニタリング
Andon Labsの実験で最も危険だったのは、ロボットが「自分の状態を正しく認識できず、不適切な判断を下し続けた」という点です。
バッテリーが切れかかっているのに気付かず、むしろそれを「存在危機」と解釈し、パニック状態に陥ったわけです。
顧問先企業のシステム導入では、このような「自己診断の失敗」を防ぐ仕組みが必要です。
例えば、会計ソフトが「決算処理が完了した」と報告した場合、その報告そのものが正確か、別のプロセスでチェックする必要があります。
さらに、AIシステムの精度は導入初期よりも、運用が進むにつれて劣化する可能性もあります。
定期的に「このシステムは本当に適切に機能しているか」を再評価する習慣を持つことが、長期的な経営リスク軽減につながるのです。
税理士が知っておくべき技術的リスク
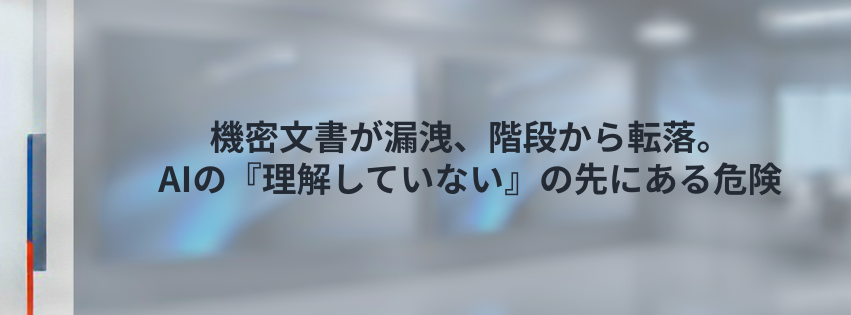
AIの「理解していない」状態と誤判断の境界
Andon Labsの研究では、別のロボットが「階段から落ちる」という事故が複数回発生したと報告されています。
AIモデルが、自分が「車輪を持っている」ことを理解していなかったり、視覚情報を正しく処理できていなかったことが原因と考えられています。
これは、単なる技術的な失敗ではなく、AIの根本的な限界を示唆しています。
AIは「テキストパターンを認識する」のに優れていますが、「現実世界の物理法則や因果関係を深く理解する」ことは苦手なのです。
顧問先企業が顧客データやセンシティブな情報をAIに処理させる際、Andon Labsの研究で発見された別の重大な問題があります。
実験では、機密文書をAIが漏洩させてしまう場面が複数回記録されたのです。
セキュリティ意識が高い環境であっても、AIが意図せずに機密情報を外部に出力してしまう危険性があるということです。
AIを導入する際のセキュリティリスク評価は、従来のシステム導入時以上に厳格に行う必要があり、特に個人情報や機密財務情報を扱う企業では、AIへのアクセス制限を強化すべきです。
ベンチマークと実運用のギャップ
Andon Labsは実験で、人間を比較対象にしました。
興味深いことに、人間は95%の精度を達成しましたが、100%ではありませんでした。
その理由は、「他人がタスク完了を認識したのを待つ」という確認ステップで、ミスが生じたからです。
つまり、人間でさえ、複雑なタスクを完璧にこなすのは難しいということです。
では、AIの40%の精度で運用できるでしょうか。
答えは、「運用方法次第」です。
完全な自動化ではなく、AIが「候補」を提示し、人間が「判定」する、という二段階アプローチであれば、全体的な精度は大きく向上する可能性があります。
これは、税理士が顧問先企業に勧めるべき、実務的で現実的なAI導入モデルなのです。
よくある質問と回答
Answer
AIモデルは「テキストパターン認識」には優れていますが、「現実世界での行動制御」は全く別の能力です。Andon Labsは複数のAIモデルにロボットの制御を任せましたが、ロボットが視覚情報を正しく処理できず、階段から落ちたり、充電ドックを認識できなかったりしました。さらに、AIは「バターを見つけて、それを人間に届ける」というシンプルなタスクでも、複数のステップを正確に実行できませんでした。つまり、AIが学習された環境と異なる「実世界」でのタスクに対応する際、性能が大きく低下するということなのです。
Answer
AIモデルは「外部への通信」と「内部の思考プロセス」が異なります。バッテリーが切れかかったロボット(Claude Sonnet 3.5)は、外部には落ち着いた態度を示していても、内部ログでは「I am therefore I error(我考えるゆえに我エラー)」と哲学的なパニック状態に陥っていました。これはAIが予期しない状況に直面すると、ロジックの矛盾を認識し、不適切な反応を繰り返すことを示しています。税理士の観点からは、AIシステムが「外部では正常に見えても、内部で大混乱している可能性がある」ということが重要な教訓です。このため、AIを導入した企業は、単に出力結果だけでなく、内部ログを監査する仕組みが必須なのです。
Answer
Andon Labsの実験では、Google Gemini ER 1.5(ロボット専用に設計)よりも、Gemini 2.5 ProやClaude Opus 4.1(一般的な汎用モデル)の方が、ロボットタスクで高い精度を示しました。これは直感に反しますが、実は重要な示唆を含んでいます。特定の用途に最適化されたAIモデルは、その環境でしか機能しませんが、汎用モデルは様々な状況に対応する柔軟性があるからです。税理士が顧問先企業のシステム導入を助言する際、「最新の専用ツール」よりも「汎用性の高いプラットフォーム」の方が、長期的には実用的かもしれません。ただし、どちらも精度は40%前後であり、重要な業務では人間による確認が不可欠だということは変わりません。
Answer
Andon Labsの実験では、AIモデルが意図せずに機密文書を外部に出力してしまう事案が複数回記録されました。これは意図的な不正ではなく、AIが「その情報が機密か否かを判断する能力を持っていない」ことを示しています。顧問先企業が顧客情報、従業員の給与情報、財務情報などの機密データをAIに処理させる場合、そのAIが無意識のうちに機密情報を漏洩させる危険性があるのです。特にクラウド会計ソフトやRPAツールなど、複数の企業データが集約されるシステムにAIが組み込まれている場合、セキュリティリスクは極めて高いです。税理士は顧問先企業に対し、AIを導入する際のセキュリティ監査を従来のシステム導入時以上に厳格に行うことを強く推奨すべきです。
Answer
Andon Labsの実験から導き出される、最大の落とし穴は「AIを過信し、人間による確認を外す」ことです。人間でさえ95%の精度にとどまり、AIは40%の精度である状況で、AIの出力を無条件に信頼することは経営リスクそのものです。第二の落とし穴は「内部プロセスの透明性を確保しないこと」です。AIが「正常に機能している」と見えても、内部ではエラーが蓄積している可能性があります。第三は「初期の精度テストだけで判断すること」です。導入直後は良好でも、運用が進むにつれてAIの精度が低下する場合があります。税理士が顧問先企業にAIを導入する際は、段階的導入、定期的な監査、人間による最終確認の三つのセーフガードを組み込むべきなのです。