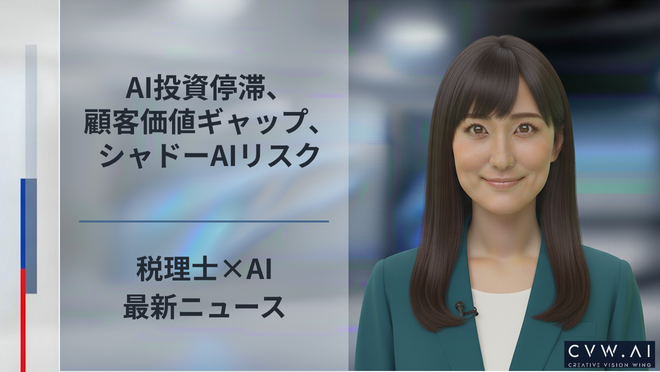税理士のみなさん、最新記事「AI value remains elusive despite soaring investment」は読みましたか?
この記事は、AI投資が拡大している一方で、多くの企業がまだ顧客価値を感じられていないという現状を伝えています。英国のRed Hatが実施した調査によれば、約9割の企業がAI導入による成果を実感できておらず、コストや人材の問題が障壁になっているとのことです。税理士や会計士としても見逃せない内容です。
元記事を5つのポイントで要約
- AI投資は急増中にもかかわらず、89%の企業が顧客価値を感じられていない。
- 導入障壁の上位は「コスト」「データ安全性」「システム統合の難しさ」。
- 83%の企業が「シャドーAI(未承認AIツールの使用)」を認識。
- 84%がオープンソースをAI戦略の中核に位置付けている。
- AI人材の不足が依然として深刻な課題に。
税理士にとっても、AIを「使いこなす力」が求められる時代です。ここでは、会計や税務の現場に直結するヒントを整理しました。
AI投資と税理士業務の今

AI投資が加速している現実
企業はAI投資を2026年までに32%増やす予定です。クラウド化や仮想化も同時に進んでおり、税理士として関係する取引先でもAI導入が進む可能性が高いでしょう。たとえば、AIを活用した経費精算や自動仕訳ツール(freee、マネーフォワードクラウドなど)をクライアントが導入するケースが今後増えるはずです。
税務顧問としては、「AI導入によるコスト増」が損金算入できるか、どのような投資勘定に分類するべきかなど、会計的なアドバイスが求められます。
AI投資格差が示すリスク
AIに大規模投資を行う企業が増える一方で、成果が出ていない状況は「投資効率」の問題を示唆しています。税理士として、投資後のROI(投資対効果)や減価償却の扱い、税務上のリスクヘッジをサポートすることが重要です。AI投資の見えないリターンを数値化できる会計力が、次の差別化ポイントになります。
「シャドーAI」がもたらすリスク

無許可AI利用の現場実態
調査では、83%の企業で「社員が勝手にAIツールを使っている」との回答がありました。これは税務・会計の世界でも起こり得る現象です。例えば、経理担当者がチャットAIで取引文書を要約したり、請求書データを変換したりするケースです。しかし、顧客や社内の機密情報が漏えいする危険性もあります。
税理士としては、顧問先に対して「AI利用方針の策定」や「情報管理ルール」の整備を促すことが求められます。
情報保護の観点からのサポート
クラウド会計やAI記帳ツールを使う際も、データ保存先のサーバーがどこにあるか、利用規約上どのように扱われるかなどは慎重に確認するべきです。
| 項目 | 確認ポイント | 税理士の対応 |
|---|---|---|
| データ管理 | 保存・共有範囲 | 契約時のリスク説明 |
| AI利用規約 | 第三者データ使用の有無 | 顧問先に注意喚起 |
| 費用区分 | AI使用料・ライセンス料 | 会計処理の助言 |
オープンソースが鍵になる

オープンソース活用の意義
84%の企業がAI戦略に「オープンソース」を重視しているという点も注目です。税理士事務所においても、オープンソース系ツール(Python、PostgreSQL、Linuxなど)を活用したコスト削減や業務自動化は有効です。
例えば、Pythonでの「自動仕訳スクリプト」や、「確定申告データの再利用スクリプト」を活用することで、人的ミスを減らし迅速な対応が可能になります。無料で活用できるオープンソース技術は、税理士の生産性向上の切り札です。
AIとオープン環境の親和性
AIモデルの構築や運用も、オープンソース環境上での実行が一般化しています。これは監査証跡を残しやすく、透明性の面で大きな利点があります。税務データ分析や不正検知AIを導入する場合も、オープン環境を選択することで、説明責任を果たす監査体制を整えやすいでしょう。
AI人材不足にどう向き合うか

税務事務所に訪れる「スキルシフト」
AIを使いこなすには、税理士側もITリテラシーを磨く必要があります。特に、データ処理やRPA(ロボット業務自動化)ツールの理解が、将来的な業務効率化に直結します。AIアナリストやAI会計コンサルタントなど、新しい職域も現れています。
税理士事務所では、アシスタントに「ChatGPT」や「Microsoft Copilot」などの支援AIを安全に導入し、経理補助業務を効率化する環境を作るのが鍵となります。
中小事務所でもできるステップ
大手事務所でなくても、次のようなステップから始められます。
- AI利用ルールを明文化(外部送信データを明示)。
- 無料Pythonコードで日報・請求処理を自動化。
- AIツール利用履歴の見える化。
これだけでも、少人数体制の事務所でも「AI対応力の高さ」をアピールできます。
英国の動向から学ぶ戦略
AI導入は「構造改革」の一歩
記事では、英国ではAIとセキュリティがIT投資の最優先分野とされています。税務の分野では、これを「内部統制の再設計」と読み替えることができます。AIの活用は単なる効率化ではなく、企業経営の信頼性を高めるための基盤づくりです。
税理士としても、AIを使った「内部統制強化支援」サービスを提供できれば、新しい顧問価値につながります。
今後の方向性
英国の調査企業の83%が「自国はAI強国になれる」と答えています。日本でも同様に、DX推進とともにAI利用の増加が予想されます。税理士業界もAIとの共存・協働に踏み出す時期に来ています。
AIを正しく理解し、活用ルールを策定することで、「効率化×信頼性」を両立した新時代の会計サービスを構築できます。AIに仕事を奪われるのではなく、AIとともに拡張する「新しい税理士像」が問われています。
よくある質問と回答
Answer シャドーAIとは、企業が正式に承認していないAIツールやサービスを従業員が個人的な判断で業務に利用することを指します。普段使われるツールとしては、ChatGPTやGemini、Microsoft Copilotなどの生成AI、画像作成AIや各種自動化ツールが含まれます。これらは業務効率の向上のために使われやすいですが、情報管理面では注意が必要です。
Answer 最大のリスクは「情報漏洩」です。業務で使うAIに機密データや個人情報を入力することで、第三者のサーバーに情報が記録される危険性があります。また、生成AIが誤った内容を出力し、そのまま業務文書に採用するとコンプライアンス問題に発展することもあります。最悪の場合、会社の機密技術が外部に流出する恐れも生じます。
Answer 税理士事務所でも、経理担当者がチャットAIで領収書内容を自動要約したり、申告用データ作成を補助するケースが増えています。また、会計書類の自動分類や監査資料の集計に、Microsoft CopilotやGoogle Bardを無許可で使うなどの事例もあります。こうした使い方が社内ルールに違反する場合、顧客情報漏洩や運用リスク増加につながります。
Answer 実際に発生した事例として、従業員が社内コードをChatGPTに入力し、ソースコード流出や機密情報漏洩を招いたケースがあります。生成AIの脆弱性によるプロンプト漏洩事件なども報告されており、技術的な不備や監視不足が原因で情報が外部に出てしまうことがあります。税理士業界でも同様のリスクが想定されます。
Answer まずはAIツール利用の社内ルールを策定し、従業員教育を徹底することが第一歩です。許可されたAIツールのみを使用する体制づくりを進めましょう。社内データの管理や保存場所の把握、AIの利用履歴の記録も効果的です。加えて、社外サービスと連携する場合は利用規約やプライバシーポリシーの確認を必須とし、リスクの低減に努めることが重要です。