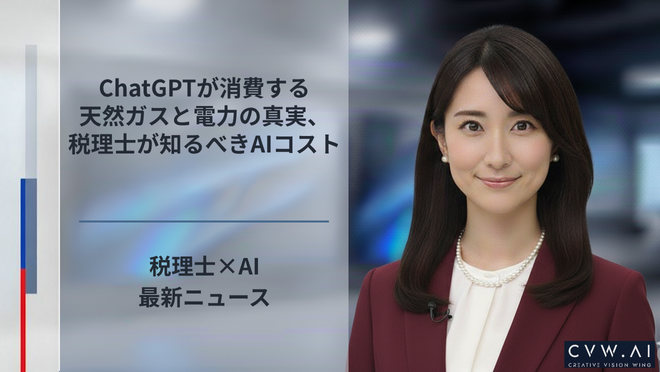税理士のみなさん、最新記事「Your AI tools run on fracked gas and bulldozed Texas land」は読みましたか?
TechCrunchが報じた記事は、私たちが日々使っているChatGPTやその他のAIツールが、実は膨大なエネルギーを消費し、その多くが天然ガスによる発電で賄われているという事実を明らかにしています。税理士業界でもAI活用が進む中、そのコストや環境負荷の裏側を知っておくことは、今後のビジネス判断において重要な視点となるでしょう。
元記事を5つのポイントで要約
- AI企業が米国テキサス州やルイジアナ州などに巨大データセンターを建設し、天然ガス(フラッキング採掘)を直接利用して電力を確保している
- OpenAIのStargateデータセンターは900メガワット、Poolsideの「Horizon」プロジェクトは2ギガワット(フーバーダムの全発電容量に相当)の電力を消費する
- 地域住民は環境破壊、騒音、水不足などの問題に直面しており、事前の相談もなく建設が進められたことに不満を持っている
- AI企業は中国との競争を理由に天然ガス発電の拡大を正当化しているが、契約期間終了後の電気料金高騰など地域住民へのリスクが懸念されている
- 既存の電力インフラの活用やピーク時の消費削減で対応可能という研究結果もあるが、企業は新規のガス発電施設建設を優先している
AIツールの裏側で起きていること
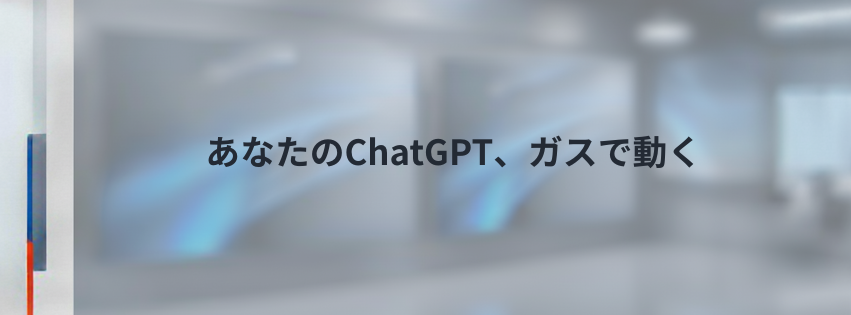
毎日使っているChatGPTやClaude、Microsoft Copilotなどのツール。
便利ですよね。
でも、その裏で何が起きているか考えたことはあるでしょうか。
フラッキングガスで動くAIインフラ
記事によると、AI企業は次々と巨大なデータセンターを建設しています。
その規模は想像を超えるもの。
例えばPoolsideという企業がテキサス州に建設中の「Horizon」プロジェクトは、500エーカー以上の土地を使い、2ギガワットの電力を生み出す計画です。
これはフーバーダムの全発電容量に匹敵します。
そして電力源は天然ガス。
それも、地下深くに高圧の水と化学物質を注入して岩盤を砕き、ガスを取り出す「フラッキング(水圧破砕法)」という手法で採掘されたものです。
OpenAIのCEOサム・アルトマンは「私たちはこのデータセンターを動かすためにガスを燃やしている」と率直に認めています。
Meta、xAIも同じ道を進む
OpenAIだけではありません。
Metaはルイジアナ州に100億ドル規模のデータセンターを建設予定で、そのために電力会社Entergyが32億ドルを投じて3つの大型天然ガス発電所を建設します。
イーロン・マスクのxAIも、メンフィス施設でフラッキング由来のガスを使用する電力を購入しています。
税理士業務で使うfreeeやマネーフォワード、弥生会計のクラウド版も、実はこうしたデータセンターのどこかで動いています。
私たちが月次監査の資料をクラウドで共有したり、AIで仕訳を自動化したりする度に、どこかでガスが燃やされているわけです。
地域住民が抱える深刻な問題
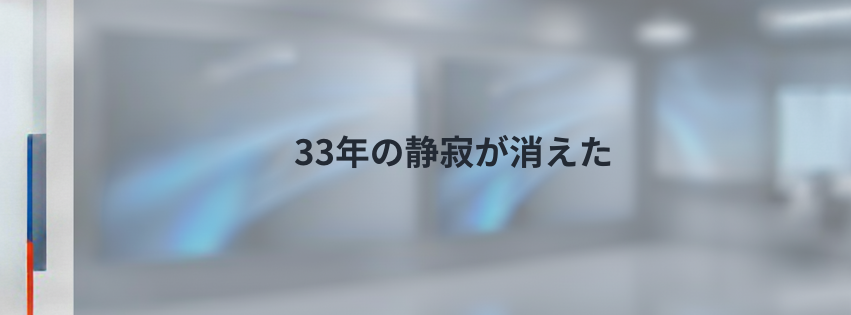
データセンター建設による影響は、数字だけの話ではありません。
実際にそこで暮らす人々の生活が変わってしまっています。
静けさが奪われた日常
テキサス州アビリーンのStargateデータセンターの向かいに住むアーリーン・メンドラーさんは、33年前に「平和、静寂、安らぎ」を求めてこの地に移住しました。
しかし今では、建設工事の騒音が絶えず、夜景は明るい照明で台無しになってしまったと話しています。
「誰も私たちに意見を聞いてくれなかった」。
この言葉が、すべてを物語っているでしょう。
広大なメスキートの茂みが重機で撤去され、そこに巨大な建物が建ち並ぶ。
地域の風景が一変する様子を、住民は何もできずに見守るしかありませんでした。
水不足への不安
もう一つの深刻な問題が水です。
テキサス州西部は干ばつが多い地域。
アルトマンが訪問した時点で、市の貯水池は約半分しか水がなく、住民は週2回しか屋外での水やりができない制限下にありました。
データセンターの冷却システムには大量の水が必要です。
Oracleは初回に100万ガロンの水を使い、その後は年間12,000ガロンで済むと主張していますが、カリフォルニア大学リバーサイド校のシャオレイ・レン教授は「これは誤解を招く数字だ」と指摘しています。
電力生成自体にも水が必要なため、間接的な水消費量はもっと多いのです。
税理士業務への影響と考えるべきこと
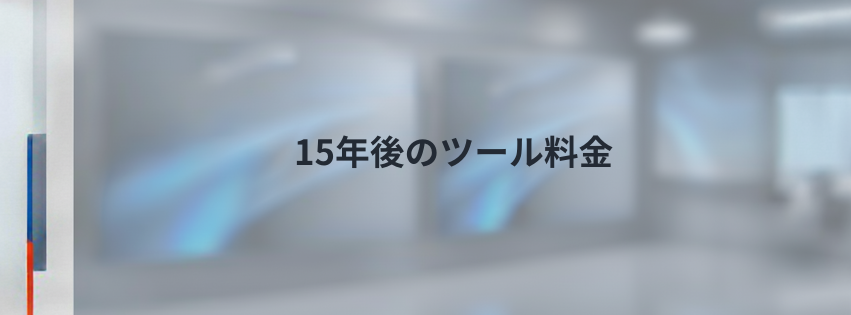
では、この問題が税理士業務とどう関係するのでしょうか。
実は思っている以上に深い関わりがあります。
AIツールのコストは今後上がる可能性
記事では、AI企業と電力会社との契約期間が15年であることが指摘されています。
Metaはルイジアナ州の発電コストを15年間保証する契約を結んでいますが、その後はどうなるのか。
契約終了後、地域住民の電気料金が高騰する可能性が懸念されています。
そして同時に、AI企業側もエネルギーコストの上昇に直面するでしょう。
それは当然、私たちが使うツールの料金に反映されます。
freeeの月額料金、ChatGPT Plusの月額20ドル、Microsoft 365 Copilotの月額30ドル。
これらが将来的に値上がりする可能性は十分にあるのです。
事務所の経費計画を立てる際、「AIツールのコストは固定ではない」という視点を持っておく必要があります。
クライアントへの説明責任
環境への配慮を重視する企業が増えています。
ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まる中、「使っているツールがどんな環境負荷を持っているか」を気にするクライアントも出てくるでしょう。
例えば、クライアント企業がサステナビリティレポートを作成する際、「会計処理に使用しているクラウドツールの環境負荷」について質問されるかもしれません。
税理士として、単に数字を処理するだけでなく、使用するツールの背景まで理解しておくことが、これからの顧問業務では求められる時代になりつつあります。
AI依存のリスクを再考する時期

記事の中で特に印象的だったのは、「これがバブルだったら、その崩壊は美しくない」という指摘です。
相互依存の連鎖構造
AI業界は複雑な相互依存関係にあります。
OpenAIはMicrosoftに依存し、MicrosoftはNvidiaに依存し、NvidiaはBroadcomに依存し、Broadcomはデータセンター運営会社に依存し、その運営会社はOpenAIに依存する。
Financial Timesは、「この基盤が崩れたら、高額なインフラだけが残される」と警告しています。
税理士事務所でも同じことが言えるでしょう。
クラウド会計ソフト、AI仕訳、自動化ツール。
便利だからと次々に導入していくと、それらへの依存度が高まります。
もしサービス提供会社が事業を縮小したり、料金を大幅に値上げしたりした場合、業務が回らなくなるリスクがあるのです。
代替手段の確保という視点
デューク大学の研究によると、電力会社は年間を通して平均53%の発電容量しか使っていないそうです。
つまり既存のインフラをうまく活用すれば、新たな発電所を建設しなくても対応できる可能性があるということ。
税理士業務でも同じ考え方ができます。
すべてをAIに任せるのではなく、従来の手法とのバランスを取る。
ピーク時の負荷を分散させるために、業務フローを工夫する。
こうした柔軟性が、長期的には事務所の安定運営につながるはずです。
| リスク項目 | 具体的な影響 | 対応策 |
|---|---|---|
| コスト上昇 | AIツールの月額料金値上げ | 複数ツールの価格比較、年間契約での固定化検討 |
| サービス停止 | データセンター障害時の業務停止 | オフライン作業可能な環境の整備 |
| 環境負荷 | クライアントからの説明要求 | 使用ツールの環境方針の把握 |
| 依存度増加 | 特定ツールなしでは業務不可 | 手作業でも対応可能な体制維持 |
今、税理士が持つべき視点
この記事から学べることは多岐にわたります。
コストの可視化と長期計画
まず、AIツールの導入コストを単年度で考えるのではなく、5年、10年のスパンで見ること。
初期費用だけでなく、ランニングコスト、将来的な値上げリスク、代替ツールへの移行コストまで含めて検討する必要があります。
例えば事務所で会計ソフトを選ぶ際、「今月はキャンペーンで初期費用無料」といった短期的なメリットだけで決めていませんか。
長期的な視点で見れば、サポート体制、データ移行の容易さ、料金改定の頻度なども重要な判断材料になります。
クライアントとの対話の質を高める
環境問題に関心を持つクライアントが増えている今、税理士もその視点を持つべきでしょう。
単に税務申告を行うだけでなく、「御社の業務で使用しているツールの環境負荷」「カーボンニュートラルへの取り組み」といった話題にも対応できる知識が求められます。
特に上場企業や大手企業の関与先では、ESG報告が義務化される流れにあります。
税理士がその一歩先を理解しておくことで、提案の幅が広がるはずです。
技術への健全な距離感
AIツールは確かに便利です。
仕訳の自動化、領収書のOCR読み取り、税務相談のサポート。
業務効率は格段に上がります。
しかし、その裏側で何が起きているかを知ることも大切。
環境負荷、地域住民への影響、エネルギー問題。
こうした視点を持つことで、「本当に必要なAI活用とは何か」を冷静に判断できるようになります。
すべての作業をAI化する必要はありません。
人間の目で確認すべきところ、AIに任せていいところ。
その線引きができる税理士こそが、クライアントから信頼される存在になるでしょう。
まとめに代えて
今回のTechCrunchの記事は、私たちに重要な問いを投げかけています。
便利なツールを使うことは悪いことではありません。
しかし、その便利さがどこから来ているのか、誰がそのコストを負担しているのか、そして将来的にどんなリスクがあるのか。
こうしたことを考える姿勢が、プロフェッショナルとして求められています。
税理士は数字を扱う専門家ですが、同時に経営のアドバイザーでもあります。
AIツールのコスト、環境負荷、持続可能性。
これらの視点を持つことで、クライアントにより深い価値を提供できるはずです。
目の前の効率化だけでなく、5年後、10年後の事務所運営を見据えた判断をしていきましょう。
ChatGPTで仕訳を確認する時、freeeで月次資料を作る時、少しだけでも「このツールはどこで動いているんだろう」と考えてみてください。
その小さな意識の変化が、より賢明な経営判断につながっていくはずです。
よくある質問と回答
Answer AIツール自体が悪いわけではありません。 問題は、その電力源が天然ガスなどの化石燃料に依存している点です。 税理士事務所がfreeeやマネーフォワードを使うこと自体は業務効率化に必要ですし、適切な利用であれば問題ありません。 ただし、将来的にはツール提供企業が再生可能エネルギーへの転換を進めているかどうかを確認する視点も持っておくとよいでしょう。 クライアントから環境配慮について質問された際にも、知識として答えられる準備をしておくことが大切です。
Answer 十分にあり得ます。 記事で指摘されているように、AI企業と電力会社との契約は多くが15年期限となっています。 契約終了後はエネルギーコストが上昇する可能性があり、それはサービス料金に反映されるでしょう。 実際、ChatGPTやMicrosoft 365などのサブスクリプションサービスは、過去にも値上げを実施しています。 税理士事務所としては、主要ツールの料金動向を定期的にチェックし、予算計画に余裕を持たせておくことをおすすめします。 また、複数の会計ソフトを比較検討し、いつでも乗り換えられる準備をしておくことも有効な戦略です。
Answer まずは正直に、現状のAIツールの多くが化石燃料由来の電力で動いていることを説明しましょう。 その上で、各ツール提供企業の環境方針を確認してお伝えするとよいでしょう。 例えばMicrosoftは2030年までにカーボンネガティブを目指すと宣言していますし、Googleも再生可能エネルギー100パーセントを目標に掲げています。 「完全にクリーンとは言えませんが、企業側も改善に取り組んでいます」という誠実な回答が信頼につながります。 また、事務所内でのペーパーレス化やリモート会議の活用など、他の環境配慮の取り組みも合わせて説明すると説得力が増すでしょう。
Answer 完全にAIを排除する必要はありませんが、バランスを取ることが重要です。 まず、重要な判断や最終チェックは必ず人間の目で行うルールを徹底しましょう。 AIの仕訳提案をそのまま承認するのではなく、内容を確認する習慣をつけることです。 また、クラウドサービスに障害が発生した場合の代替手段を用意しておくことも大切です。 例えば、重要な顧客データはローカルにもバックアップを取る、基本的な計算はExcelでもできるようにしておくなど、オフライン環境でも最低限の業務が継続できる体制を整えておきましょう。 技術は便利な道具ですが、それに完全に依存しない柔軟性が事務所の resilience(回復力)を高めます。
Answer 規模に関係なく、知識として持っておくことは重要です。 特に今後、中小企業でもESGへの取り組みが求められる時代になってきます。 顧問先から「うちの会社も環境配慮を始めたいが何から手をつければいいか」と相談された際、税理士が基礎知識を持っていれば適切なアドバイスができます。 また、若い世代の経営者ほど環境問題への関心が高い傾向にあります。 新規顧客獲得の際にも、「環境問題にも理解がある税理士」という印象は好感度につながるでしょう。 大規模な対策を講じる必要はありませんが、社会のトレンドとして押さえておくことで、顧問先との会話の幅が広がり、信頼関係の構築にも役立ちます。