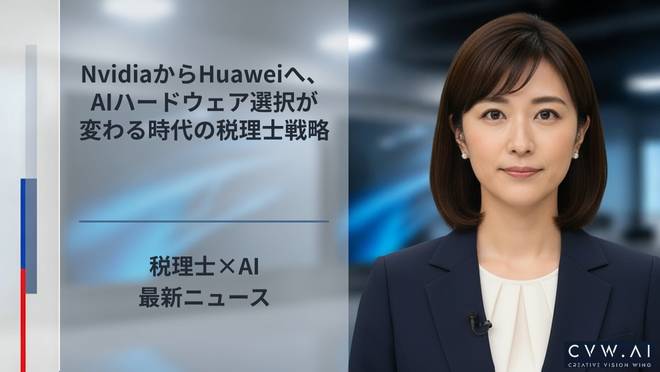税理士のみなさん、最新記事「Migrating AI from Nvidia to Huawei: Opportunities and trade-offs」は読みましたか?
この記事では、AI業界におけるハードウェア選択の大きな転換点について解説しています。長年主流だったNvidiaのGPUから、中国Huaweiの代替技術への移行を検討する企業が増えている背景と、その判断に必要な情報がまとめられています。
**元記事を5つのポイントで要約。**
- NvidiaのGPUはAI開発の標準的な選択肢だったが、HuaweiがAscend NPUという対抗技術を提供し始めた
- Huaweiへの移行は、供給リスクの分散やコスト削減、地域戦略との整合性などのメリットがある
- ただし移行には200人規模のエンジニアと6ヶ月の期間が必要で、性能も約90%に留まるケースがある
- TikTokを運営するByteDanceなど、実際にHuaweiチップでモデル訓練を行う企業が出てきている
- 移行判断には、推論作業の比重、地域性、エンジニアリング体制などを総合的に評価する必要がある
AIハードウェア選択が税理士業務に与える影響
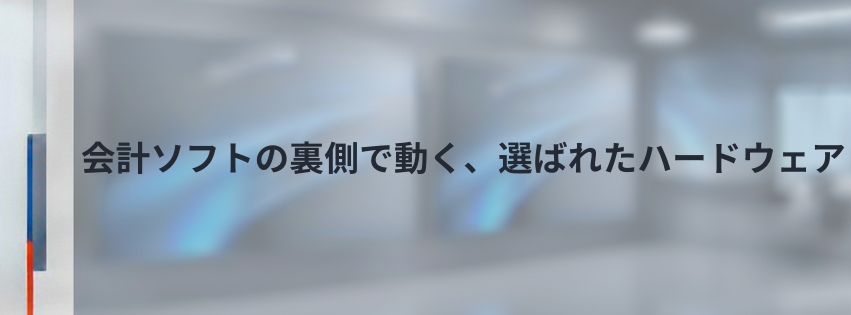
税理士事務所でAI導入を検討している方にとって、このハードウェアの話は一見関係なさそうに見えるかもしれません。
しかし実は、皆さんが使うクラウド会計ソフトやAI税務ツールの裏側で動いているのが、まさにこうしたハードウェアなのです。
会計ソフトのAI機能とハードウェアの関係
freee、マネーフォワード、弥生会計といった主要な会計ソフトには、今やAI機能が標準搭載されています。
自動仕訳提案、領収書のOCR読み取り、異常値検知など、日々使っている機能の多くがAI技術に支えられているのです。
これらのAI機能を動かすには、膨大な計算処理が必要になります。
その計算を担っているのが、NvidiaやHuaweiのようなハードウェアメーカーの製品。
ソフトウェア提供会社がどのハードウェアを選ぶかによって、処理速度、コスト、そして最終的にはサービス料金にも影響が出てくるのです。
例えば、大量の決算書データを分析して業界平均と比較する機能や、過去の申告データから最適な節税プランを提案する機能。
こうした高度なAI機能を安定的かつ低コストで提供できるかどうかは、裏側のハードウェア選択次第とも言えます。
クラウドサービスの選択肢が広がる意味
記事で触れられているように、AI業界ではNvidia一強の状況から選択肢が増えつつあります。
これは税理士業界にとっても朗報でしょう。
複数のハードウェア選択肢があることで、ソフトウェア提供会社は価格交渉力を持てます。
結果として、会計ソフトやAI税務ツールのコストダウンにつながる可能性があるのです。
また、供給リスクが分散されることで、サービスの安定性も向上します。
実際、中国市場向けのクラウド会計サービスを展開する企業では、すでにHuaweiのクラウドインフラを採用しているケースもあります。
グローバルに展開する会計ソフト会社にとって、地域ごとに最適なハードウェアを選べることは大きなメリットなのです。
なぜ今「一社依存」のリスクが問題なのか
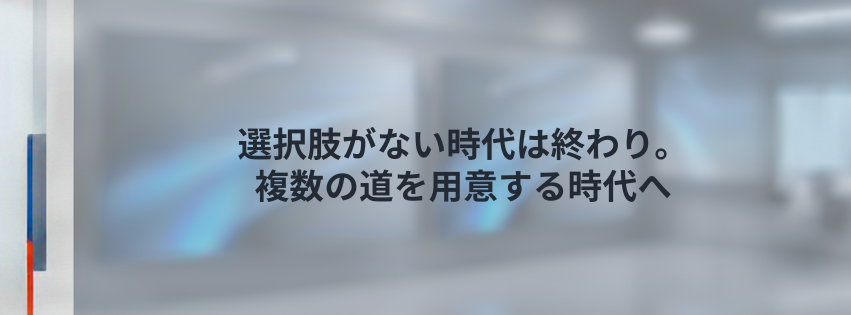
記事の中で強調されているのが、単一ベンダーへの依存リスクです。
これは税理士事務所の業務システム選択においても、非常に重要な視点になります。
特定ツールへの依存が生む脆弱性
多くの税理士事務所では、特定の会計ソフトやe-Taxシステムに業務が深く依存しています。
もしそのシステムに障害が発生したら、業務が完全にストップしてしまうでしょう。
実際、過去にはクラウド会計サービスの大規模障害により、確定申告期に作業ができなくなったケースもありました。
また、特定のソフトウェア会社が大幅な値上げを行った際、多くの事務所が移行の困難さから受け入れざるを得なかったという事例もあります。
AIツールを含めたシステム選択では、代替手段を確保しておくことが重要です。
記事で紹介されているByteDanceの事例のように、主要システムとは別に代替プラットフォームでの検証を行っておく。
こうした「デュアルスタック戦略」は、税理士事務所の業務継続計画においても参考になります。
コスト交渉力を持つための選択肢
システム選択に柔軟性があると、ベンダーとの価格交渉がしやすくなります。
「他社製品への移行も検討している」という姿勢を示せるだけで、値上げを抑制できたり、より良い条件を引き出せたりするのです。
税理士事務所向けのAIツールも、今後ますます多様化していくでしょう。
ChatGPTベースのツール、Google Bardを活用したもの、独自AIエンジンを搭載したものなど。
複数のツールを試用し、比較検討する習慣をつけておくことが、長期的なコスト管理につながります。
記事では、Huaweiへの完全移行には200人のエンジニアと6ヶ月かかったとありますが、税理士事務所レベルでは、複数のクラウドツールを併用するだけで十分です。
主力ツールは継続しながら、補助的に別のAIツールを使ってみる。
そんな小さな一歩が、将来の選択肢を広げます。
AI導入のコストと効果を見極める
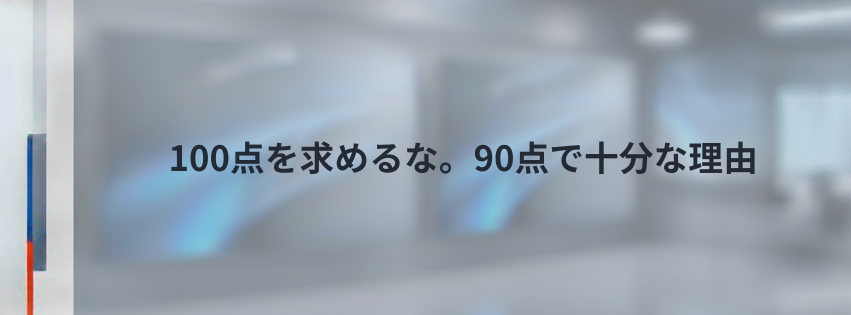
記事では、Huaweiへの移行で性能が約90%になったという事例が紹介されています。
これは税理士のAIツール選択においても、重要な示唆を与えてくれます。
100点満点を求めるより実用性重視で
AIツールを選ぶとき、ついつい最高性能のものを求めがちです。
しかし税理士業務では、100%の精度よりも、90%の精度で十分な場合が多いのではないでしょうか。
例えば、領収書のOCR読み取り機能。
最先端のAIなら99%の精度で読み取れるかもしれませんが、95%の精度でも実務上は十分です。
なぜなら、最終的には人間の目でチェックするプロセスが必要だからですね。
コストと性能のバランスを見極めることが、賢いAI導入の鍵となります。
高額なエンタープライズ版ではなく、機能を絞った手頃な価格のツールで十分な場合も多いでしょう。
記事で触れられているように、推論処理(実際にAIを使って結果を出す作業)に特化したシステムは、訓練処理よりもコスト効率が良い傾向があります。
税理士が使うAIツールは、まさにこの推論処理が中心です。
既に訓練済みのモデルを使って仕訳を提案したり、税務判断をサポートしたりするわけですから。
段階的な導入で失敗を防ぐ
記事では、移行前にパイロット版でベンチマークテストを行うことが推奨されています。
これは税理士事務所のAI導入においても、そのまま当てはまる原則です。
いきなり事務所全体で新しいAIツールを導入するのではなく、まずは一部のスタッフや特定の業務で試してみる。
例えば、確定申告シーズンの前に、数名のスタッフで新しい申告書作成支援AIを使ってみる。
実際の業務で効果を確認してから、本格導入を判断する。
Excel、freee、マネーフォワード、JDL、TKC、ミロク情報サービスなど、すでに使い慣れたツールとの連携性も重要な判断基準になります。
新しいAIツールが既存システムとスムーズに連携できるか、データの移行は簡単か。
こうした実務的な観点を、パイロット導入で確認しておくべきでしょう。
地政学リスクとシステム選択の新常識
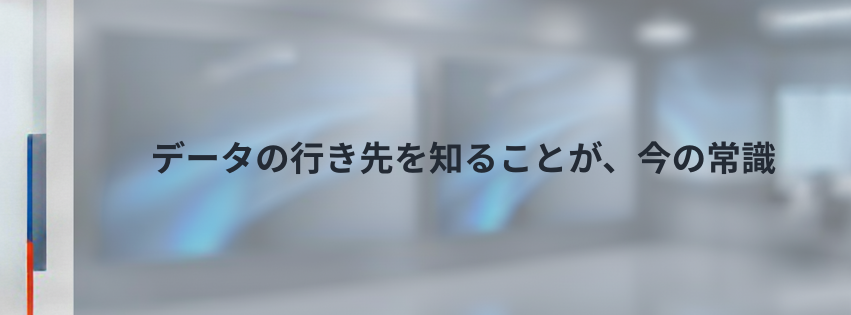
記事の背景にあるのは、米中間の技術競争という地政学的な要因です。
一見、日本の税理士には関係なさそうですが、実は無視できない影響があります。
グローバルなサプライチェーンと税理士業務
クラウド会計ソフトやAI税務ツールの多くは、海外のクラウドインフラ上で動いています。
Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloudなどが代表的ですね。
これらのサービスは、世界中のデータセンターを活用して提供されています。
その中には、記事で言及されているようなNvidiaやHuaweiのハードウェアが使われているのです。
国際的な輸出規制や供給制約が発生すると、間接的に税理士が使うツールの価格や性能にも影響が出てくる可能性があります。
また、顧客企業が中国ビジネスを展開している場合、中国国内でのデータ処理が必要になるケースもあります。
そうした際、Huaweiのようなローカルプラットフォームに対応したツールを選択する必要が出てくるかもしれません。
データ主権とセキュリティへの意識
記事では、Huaweiハードウェアに対する規制リスクについても触れられています。
税理士が扱うのは、企業や個人の機密度の高い財務データです。
どの国のどのインフラで処理されているのか、意識しておく必要があるでしょう。
日本国内のデータセンターのみでサービスを提供するクラウド会計ソフトもあれば、海外のインフラを活用するものもあります。
顧客企業のセキュリティポリシーや業種によっては、データの保管場所が重要な選択基準になります。
AIツール選択では、機能や価格だけでなく、データがどこで処理されるかという視点も持つべき時代になってきました。
特に、上場企業や金融機関の税務を扱う場合、こうした観点での質問を受けることも増えていくでしょう。
税理士が今すぐできる実践的な対策
記事の教訓を、税理士事務所の実務にどう活かせるでしょうか。
具体的なアクションプランをまとめてみました。
複数ツールの比較検討を習慣化
まず、現在使っているAIツールや会計ソフト以外にも、定期的に新しいサービスを試してみましょう。
無料トライアルを活用して、年に2〜3個は新しいツールを触ってみる習慣をつけるのです。
| 業務分野 | チェックすべきツール例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 記帳代行 | AI自動仕訳ツール複数社 | 精度、処理速度、コスト |
| 申告書作成 | 申告支援AIの新機能 | 法改正対応、使いやすさ |
| 顧客コミュニケーション | チャットボット、FAQ自動生成 | 顧客満足度、業務削減効果 |
| データ分析 | 経営分析AI、異常値検知 | 提案力向上、差別化効果 |
実際に触ってみることで、現在のツールとの違いが体感できます。
もし代替ツールの方が優れていれば移行を検討できますし、現行ツールの方が良ければ、その価値を再認識できるでしょう。
柔軟な業務設計を心がける
特定のツールに依存しすぎない業務フローを設計することも重要です。
例えば、主要な会計ソフトで作業しながらも、重要なデータは定期的にCSV形式でバックアップしておく。
AIツールの出力結果は、Excelなどの汎用フォーマットでも保存しておく。
こうした習慣があれば、万が一ツールを変更する必要が出てきても、スムーズに移行できます。
記事で紹介されたByteDanceの事例のような大規模移行ではなく、小規模な税理士事務所なら数週間で切り替えられるはずです。
また、スタッフ教育においても、特定ツールの操作方法だけでなく、AI技術の基本的な考え方を理解してもらうことが大切ですね。
「なぜこのAIはこういう提案をするのか」という原理を理解していれば、別のツールに変わっても応用が効きます。
税理士業界は今、大きな変革期を迎えています。
AIハードウェアの選択肢が広がることは、巡り巡って私たちの業務環境にも良い影響をもたらすはず。
技術の進化を味方につけて、より付加価値の高いサービスを提供していきましょう。
よくある質問と回答
Answer
完全に可能です。ただし「完全に置き換える」というより「補完的に使い分ける」という考え方が現実的です。例えば、メインの会計ソフトはfreeeで統一しながら、特定の顧客向けには弥生会計の機能を活用するといったように。最近のクラウドツールはAPI連携が充実しているので、異なるシステム間のデータ移行もそこまで難しくありません。ただし、複数システムを管理する手間が増えることは事実なので、実務的には「どの程度の顧客に対して必要か」を見極めることが大切です。従事者が3名以下の小規模事務所なら、メインツール1つに絞った方が効率的な場合もありますね。
Answer
直接的には、処理速度やコストに影響します。AIが裏側で使っているハードウェアが高性能かつ低コストなら、そのソフト自体の価格も下がる可能性があります。逆に高いハードウェアを使えば、利用料金に反映されるわけです。また、地域によってハードウェアが異なる場合、同じソフトでも国や地域によって性能にばらつきが出ることもあり得ます。中国市場向けのサービスなら高性能でも、日本向けは別のハードウェアを使っているということもあるでしょう。ただし、大手クラウド会計ソフトであれば、こうした最適化はすでに考慮されているはずです。
Answer
税務判断そのものは人間が最終決定する必要があるので、AIは「提案・サポート」のレベルで使うべきです。例えば、仕訳提案なら95%の精度で十分。人間が5%の異常値をチェックすればいいわけです。むしろ完璧さよりも「提案の速さ」や「使いやすさ」が重要な場合もあります。税務判断については、AIは過去事例の参考提示や法令改正のアラート程度と考えるべきでしょう。最終的な判断責任は税理士にあるので、AIの出力が100%正確である必要はありません。むしろ、AIが時間を節約してくれた分、より複雑な案件や顧客相談に時間を使える方が、事務所の価値向上につながります。
Answer
その通りです。繁忙期に新しいツールのトラブルに対応するのは、クライアントに迷惑がかかりますし、スタッフの負担も大きくなります。理想的なスケジュールは、確定申告が終わった4月〜7月の比較的落ち着いた時期です。この期間に複数のツールを試用して、次年度の導入を検討するという流れがいいでしょう。また、新ツール導入の際も、全員一斉ではなく、サンプル案件で試してからの段階的導入が鉄則です。ベテランスタッフ1〜2名が先に使ってみて、「これなら大丈夫」という確信が持てたら、他のスタッフに教えていくという方が安全です。
Answer
顧客によって重要度が異なります。上場企業や金融機関の顧客を扱っているなら、確実に聞かれる質問になっています。特に、情報セキュリティポリシーが厳しい大手企業の場合、「データが日本国内サーバーのみで処理されるか」を確認されるケースが多いですね。中小企業向けなら、そこまで厳密でない場合もありますが、今後はセキュリティへの関心が高まっていく傾向にあります。また、クライアント企業が国際取引をしている場合、データの国際移動に関する法的リスクも考慮する必要があります。つまり、「この情報セキュリティ対応できていますか」という相談に応じられることが、今後の税理士の付加価値になる可能性があるということです。導入するツール選択時に、こうした点を確認する習慣をつけておくと、クライアント対応もスムーズになるでしょう。