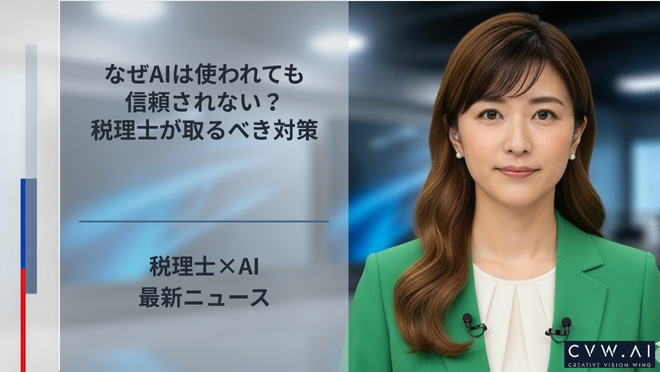税理士のみなさん、最新記事「How to fix the AI trust gap in your business」は読みましたか?
AIツールを実務で使っているのに、その判断をどこまで信頼していいのかわからない。そんな悩みを抱えている税理士の方は多いのではないでしょうか。今回の記事は、ビジネス現場で広がる「AI利用率と信頼度のギャップ」を解説し、その解決策を示しています。
元記事を5つのポイントで要約
- UAEでは97%がAIを使用しているが、84%は信頼できる使い方をされている確信がないと信頼しないと回答
- イギリスでは57%がAIを受け入れているものの、実際に信頼しているのは42%に過ぎない
- 80%の人が「より強いルールが必要」と感じており、AIの責任体制に不安を抱いている
- SleekFlow社のLei Gao氏は「普及ではなく、説明責任が今後の課題」と指摘
- 信頼構築には「透明性」「人間との協働」「継続的なチェック」の3つが重要
なぜ税理士もAI信頼ギャップに直面するのか
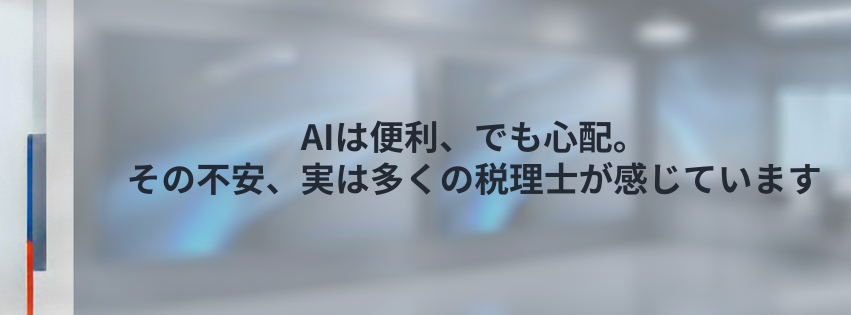
税理士業務は数字の正確性と法的な判断が求められるため、AIへの信頼問題は顧客満足度や事務所の評判に直結します。
会計ソフトのfreeeやマネーフォワードクラウド、弥生会計オンラインなど、多くの税理士事務所がすでにクラウド型のツールを導入しています。これらのツールにはAI機能が組み込まれており、仕訳の自動提案や勘定科目の推測が行われるようになりました。
しかし、実際の現場では「AIが提案した仕訳は本当に正しいのか」「この判断を顧客にどう説明すればいいのか」といった疑問が生まれています。便利だから使っているけれど、心のどこかで不安を抱えている状態です。
実務でよくある「信頼できない瞬間」
例えば、AIが経費の勘定科目を「交際費」と判断したとしましょう。しかし税理士から見れば、その取引の背景を考えると「会議費」が適切なケースがあります。こうした場面で、AIがなぜその判断をしたのか説明がないと、信頼は一気に崩れます。
記事で紹介されているKPMGの調査では、78%の人がAIによる悪影響を懸念しているとのこと。税理士業界に置き換えれば、誤った税務申告や顧客情報の漏洩といったリスクが頭をよぎるはずです。
使用率と信頼度のズレがもたらすリスク
便利だから使う、でも信頼はしていない。このギャップが続くと、いずれ大きな問題につながります。
顧客から「先生、このAIの判断は合っていますか?」と聞かれたとき、自信を持って答えられないとしたら、それは専門家としての信頼を損なうことになりかねません。またスタッフがAIツールに依存しすぎて、基本的な簿記の知識が身につかないという弊害も生まれます。
信頼できるAI活用のための3つの対策
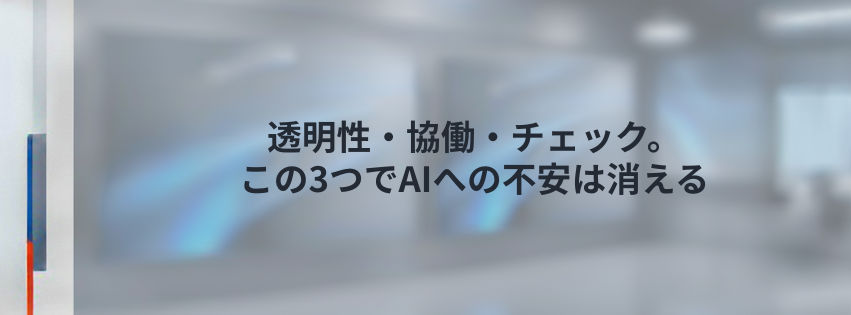
記事ではSleekFlow社のCTO、Lei Gao氏が提案する3つの解決策が紹介されています。これを税理士業務に当てはめて考えてみましょう。
①透明性の確保:AIを使っていることを明示する
顧客やスタッフに対して、どの作業をAIが行い、どの部分を税理士が判断しているのかを明確に伝えることが信頼の第一歩です。
例えば、月次レポートを作成する際に「仕訳はAIが自動提案し、税理士が全件チェックしています」と一言添えるだけで、顧客の安心感は大きく変わります。ChatGPTで税務相談の下書きを作成したなら、そのことを隠さずに「AIで作成した案を元に、税理士が法令と判例を確認しました」と説明する姿勢が大切です。
透明性がないと、いざミスが発覚したときに「AIのせいにした」と思われてしまいます。最初から「ここはAIを使っている」と明示しておけば、チェック体制への理解も得られやすくなるでしょう。
②人間の補助としてのAI:置き換えではなく協働
AIは税理士の仕事を奪うものではなく、サポートするツール。この考え方を事務所内で共有することが重要です。
記事では「AIは人間を補強すべきであり、排除すべきではない」と述べられています。税理士の場合、単純な仕訳入力や書類の整理はAIに任せ、その分、顧客との対話や経営アドバイスに時間を使える環境を作ることが理想形といえます。
freee会計のAI機能は領収書をスキャンして自動で仕訳を提案しますが、最終判断は必ず人間が行います。この「提案→確認→承認」の流れを意識的に守ることで、AIと人間の役割分担が明確になります。
③継続的なチェック:導入して終わりではない
AIツールは一度設定したら終わりではなく、定期的に精度をチェックし、改善していく必要があります。
例えば、3ヶ月ごとにAIが提案した仕訳の正解率を集計してみましょう。もし特定の取引パターンで間違いが多いなら、AIの学習データを見直すか、その部分だけ手動入力に切り替える判断が必要です。
記事では「トーン、バイアス、問題への対処方法を定期的にチェックすることが信頼維持につながる」と指摘されています。税理士業務なら、AIの提案傾向を毎月振り返り、「最近、交際費の判断が甘くなっていないか」といった視点で見直すことが該当するでしょう。
税理士事務所で実践できる信頼構築の具体策
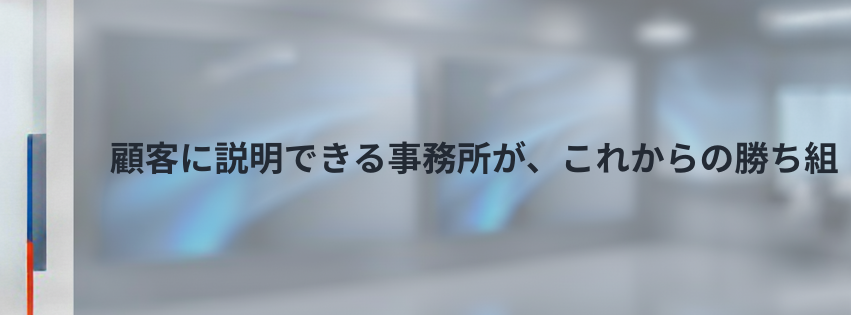
では、実際の税理士事務所では何から始めればいいのでしょうか。
顧客向けの説明資料を用意する
AIをどのように使っているのか、どんな安全対策を取っているのかを1枚の資料にまとめておくと効果的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| AI使用場面 | 領収書のスキャン、仕訳の自動提案、勘定科目の推測 |
| 税理士の確認 | 全ての仕訳を税理士が目視でチェック |
| セキュリティ | データは暗号化され、外部に漏れない仕組み |
| ミス発見時の対応 | 即座に修正し、顧客に報告 |
こうした資料を契約時に渡しておけば、「この事務所はAIを使っているけど、ちゃんと人間がチェックしているんだな」という安心感を持ってもらえます。
スタッフ教育でAIリテラシーを高める
事務所内でAIの仕組みや限界について勉強会を開くことも有効です。
「AIは過去のパターンから学習しているため、過去にない取引は苦手」「感情や文脈は読み取れない」といった基本を理解しておけば、スタッフも適切な距離感でAIと付き合えるようになります。マネーフォワードクラウド会計やChatGPTなど、実際に使っているツールの特性を具体的に共有しましょう。
また、AIが間違えた事例を集めて共有することも大切です。「こういうケースではAIが誤判断する」という知識があれば、チェックの精度も上がります。
AI時代の税理士に求められる新しい役割
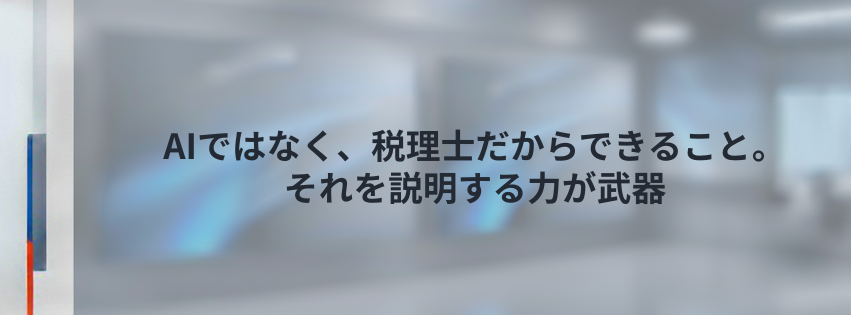
記事の最後で、Lei Gao氏は「次のマイルストーンは信頼であり、自動化が人々のために機能することを示すこと」と結んでいます。
説明できる税理士が選ばれる時代
これからの税理士には、AIをどう使っているか、なぜその判断をしたのかを明確に説明できる力が求められます。
顧客が知りたいのは「AIが何をしたか」ではなく、「税理士がどう判断したか」です。AIはあくまで道具。その道具をどう使いこなし、最終的にどんな価値を提供できるかが、税理士の腕の見せどころになります。
例えば、確定申告の時期に「今年は申告件数が多かったのですが、AIの力で効率化できたため、例年と同じスピードで対応できました」と説明すれば、顧客は納得してくれるでしょう。逆に、何も説明せずにいると「手を抜いているのでは」と疑われる可能性もあります。
信頼されるAI活用のチェックリスト
最後に、自分の事務所がAIを適切に使えているか確認するためのポイントをまとめます。
- AIが関与している作業を顧客に説明できる
- AIの提案を鵜呑みにせず、必ず人間が確認している
- AIが間違えやすいパターンを把握している
- 定期的にAIの精度を検証している
- スタッフ全員がAIの限界を理解している
- 顧客から「AIは大丈夫ですか?」と聞かれたときの回答を用意している
これらが揃っていれば、AIを使っていることが強みになります。逆に一つでも欠けていれば、そこが信頼を損なうポイントになる可能性があります。
AIは便利ですが、魔法ではありません。正しく理解し、正しく使い、正しく説明する。この3つを守れば、顧客からの信頼はむしろ高まります。記事が指摘する「AI信頼ギャップ」を埋めることができる税理士こそ、これからの時代に選ばれる専門家になるでしょう。
よくある質問と回答
Answer
透明性を持って説明すれば、むしろ評価されます。「AIで効率化した分、経営相談により多くの時間を使えます」と伝えることで、顧客はサービスの質が上がったと感じるでしょう。重要なのは、AIが提案した内容を税理士が必ず確認していることを明示することです。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計を使っている事務所が増えている今、AIの活用は時代の流れといえます。
Answer
最終的な責任は必ず税理士にあります。AIはあくまで補助ツールであり、判断を下すのは人間です。だからこそ、AIの提案を鵜呑みにせず、必ず税理士の目でチェックする体制が不可欠なのです。顧客との契約書にも「AIツールを使用するが、最終確認は税理士が行う」旨を明記しておくと安心です。万が一ミスがあった場合の対応手順も事前に決めておきましょう。
Answer
この懸念は正しいといえます。新人スタッフには、まず手入力で仕訳を学ばせ、基礎が固まってからAIツールを使わせる段階的な教育が効果的です。また、AIが提案した仕訳を「なぜその勘定科目なのか」説明させる訓練を取り入れることで、思考力を養えます。AIは便利ですが、その判断の根拠を理解できなければ、応用が利かない人材になってしまいます。
Answer
下書きとして使うこと自体は問題ありませんが、そのまま顧客に渡すのは危険です。ChatGPTは最新の税制改正や個別の事情を完全には把握できないため、必ず税理士が内容を精査し、法令や通達と照らし合わせる必要があります。また、顧客に渡す際は「AIで下書きを作成し、税理士が確認・加筆しました」と説明する透明性が信頼につながります。AIを使ったことを隠す必要はありません。
Answer
3ヶ月に一度、AIが提案した仕訳の正解率を集計してみましょう。例えば「交際費と会議費の判断」「消費税の課税区分」など、項目ごとに分析すると、AIが苦手な分野が見えてきます。マネーフォワードクラウドやfreeeには学習機能があるため、間違いを修正することで精度が向上します。また、同じような取引が続く顧問先では、AIの提案パターンを定期的に見直すことで、ミスを未然に防げます。