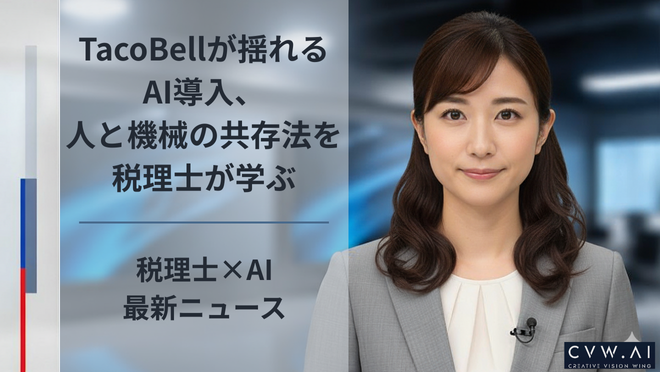税理士のみなさん、最新記事「Taco BellがドライブスルーAI導入を見直し中」(参照元:TechCrunch, 2025年8月30日 https://techcrunch.com/2025/08/30/taco-bell-is-having-second-thoughts-about-relying-on-ai-at-the-drive-through/)は読みましたか?
ファストフード大手のAI導入の葛藤は、私たち税理士や会計士のAI活用にも直結するテーマです。
まずは元記事を5つのポイントで簡単にまとめます。
- Taco BellはAIによるドライブスルー注文を500店舗以上に展開。
- 一部で18,000個の水カップ注文など「悪用」やトラブル事例が発生。
- 状況に応じてAIと人間を切り替える方針を検討中。
- 本社として全店舗一律導入はせず、フランチャイズごとの柔軟さを認める。
- 担当役員自身もAI利用に「驚き」と「失望」が混在していると発言。
この事例は、税理士や会計士がAIを導入する際の「どこまで任せるか」「どの場面で人間が介入すべきか」という大きなヒントになります。
特に、freeeやマネーフォワード、弥生会計といったツールを日常的に使用している方には、共感する部分が多いのではないでしょうか。
ここから記事を題材に、AI活用の視点を税理士の仕事と結び付けて整理していきます。
AI導入で見えた限界
AIは万能ではない現実
Taco Bellの例で明らかになったのは「AI任せにすると想定外の事態が起きる」という点です。
税務の現場でも、AI-OCRで領収書を読み取った際に誤認識することがあります。
こうした誤りをそのまま申告データに反映してしまえば、修正や顧客への再確認が必要になる状況を招きます。
AIは計算や定型処理に強い一方で、イレギュラー対応はまだ不得意です。
特に税法改正や補助金申請の細かい要件などは、柔軟な判断が欠かせません。
人の介入が必要な場面
AIが完全に「自律」して業務を任せられる範囲は限られています。 Taco Bellが「混雑時は人間に戻す」判断をしているように、税務現場でも「複雑な法人決算」「顧客特有の取引形態」では人間の知見が必要です。
会計ソフトに自動仕訳を任せる場合でも、定期的にレビューを入れ、税理士が修正を加える仕組みが重要でしょう。
AIと人の役割分担
定型業務はAIに委ねる
振込明細の仕訳や経費の自動分類といった定型作業はAIに任せるのが適しています。
freee会計の「自動で経理」や、マネーフォワードの「AI学習仕訳」はまさにこの領域をカバーしています。
これにより、記帳代行に割かれていた時間を顧客との面談や節税提案に振り分けられるのです。
判断業務は人が主導する
AIでは難しい「判断・交渉」こそ、人が担うべき部分です。
例えば、資金繰りの相談や借入計画の助言は、数値だけでなく経営者の意向や業界動向まで視野に入れなければ的確な提案ができません。
AIは助手であり、最終判断は税理士が行う構図が理想的です。
トラブル対応から学ぶ
AI利用リスクを想定する
Taco BellではAIが「18,000個の水」注文を処理しようとしたことが話題になりました。
税理士領域でも、AIが誤って仕訳や申告を処理してしまえば、税務署からの問い合わせや修正申告につながります。
あらかじめAIの誤作動リスクを想定し、チェック体制を整えておくことが必須です。
監査・レビュー体制の構築
実務で有効なのは「ダブルチェックの流れをシステム化する」ことです。
例えばfreeeやマネーフォワードではAIが提案した仕訳を「要承認」状態にしておき、人がワンクリックで確認してから確定する方式があります。
このように「AI任せ」にせず、あえて「人間の最終承認」をワークフローに組み込むことで、誤りを最小化できます。
税理士が意識すべきAI活用の7選
最後に、Taco Bellの事例から学んだエッセンスを、税理士が活かすAI活用の7つの工夫としてまとめます。
- 定型作業はAIに任せて、判断業務に時間を使う。
- AIの提案は必ずレビューを経て確定する。
- 顧客コミュニケーションは人間が担い、信頼関係を築く。
- 税法改正や補助金制度など流動的な情報は人が判断。
- 誤作動した場合のチェック・修正フローを明文化する。
- ツール(freee、弥生、マネーフォワードなど)の機能を定期的に見直す。
- AI導入で削減できた時間をコンサルティング業務に再投資する。
まとめると、Taco BellのAI活用の迷いは、税理士業務においても他人事ではありません。
私たちもツールをどう使い、どこでストップをかけるのか、その境界を設計する必要があります。
AIは仕事を奪うものではなく、専門家がより価値のある仕事に注力するための装置です。
この発想を持って日々の業務に活かしていきましょう。
よくある質問と回答
Answer AIは定型業務の効率化を促進し、経費仕訳や請求書処理などの繰り返し作業を自動化します。
これにより税理士は時間を節約し、顧客対応や節税提案など判断を要する業務により集中できる環境になります。
Answer AIの誤認識や誤処理は現実的なリスクです。
したがってAIが自動生成した仕訳やデータは必ず人間が最終チェックを行い、誤りがあれば修正する仕組みが不可欠です。
これでリスクを大幅に軽減できます。
Answer freee、マネーフォワード、弥生会計などの会計ソフトはAI搭載の自動仕訳や領収書のOCR読み取り機能を備えています。
また、MJSの「AIアシスト」のような問い合わせ対応支援ツールも使いやすくおすすめです。
Answer まずAI導入の目的を明確にし、処理対象業務や成果指標(KPI)を設定することが重要です。
さらに、AIの出力が最新の税制や会計基準に合致しているか確認し続ける体制を整える必要があります。
Answer AIが効率化した時間は顧客との面談強化や経営相談、資金繰りアドバイス等の価値提供に充てることが望ましいです。
これにより税理士自身の専門性と顧客満足度が高まります。